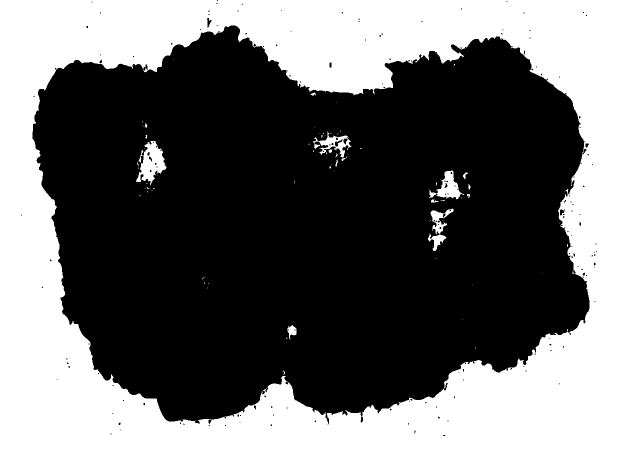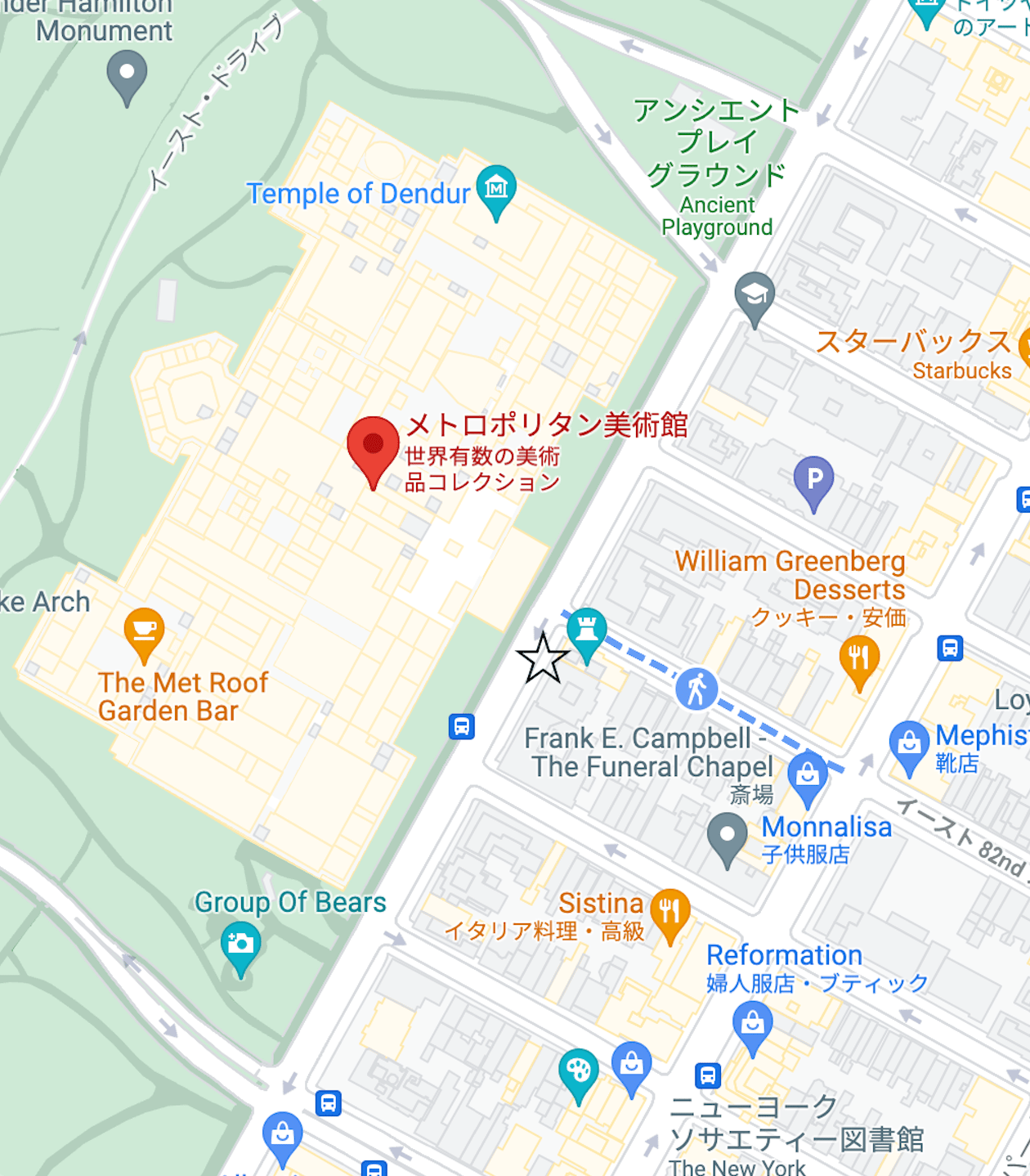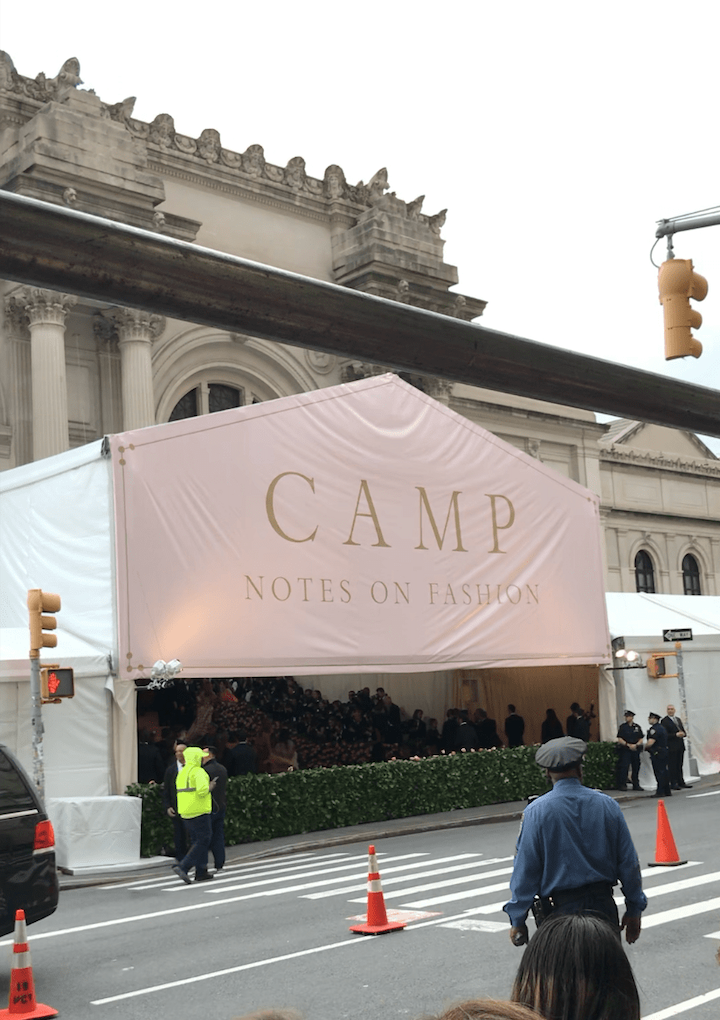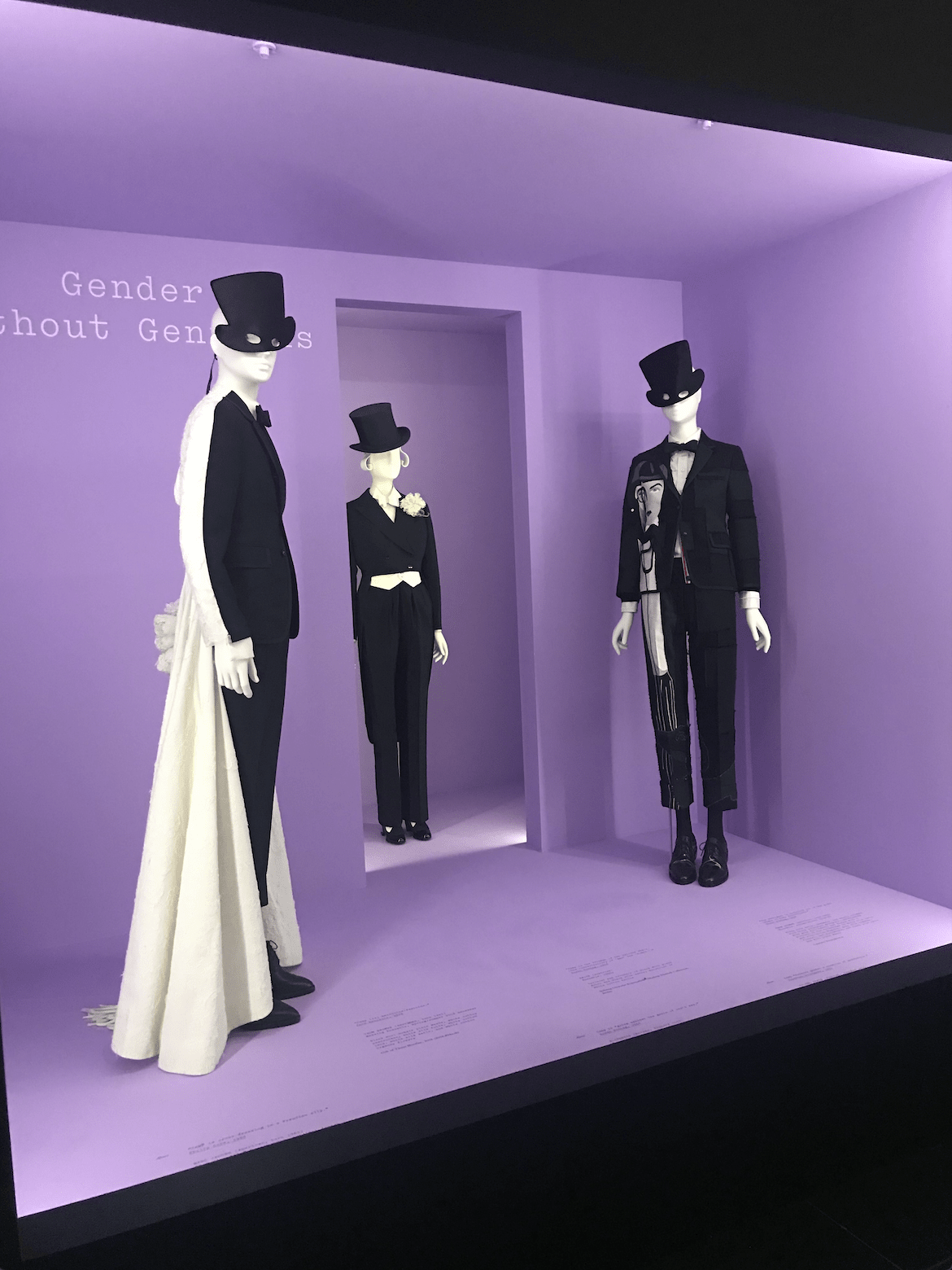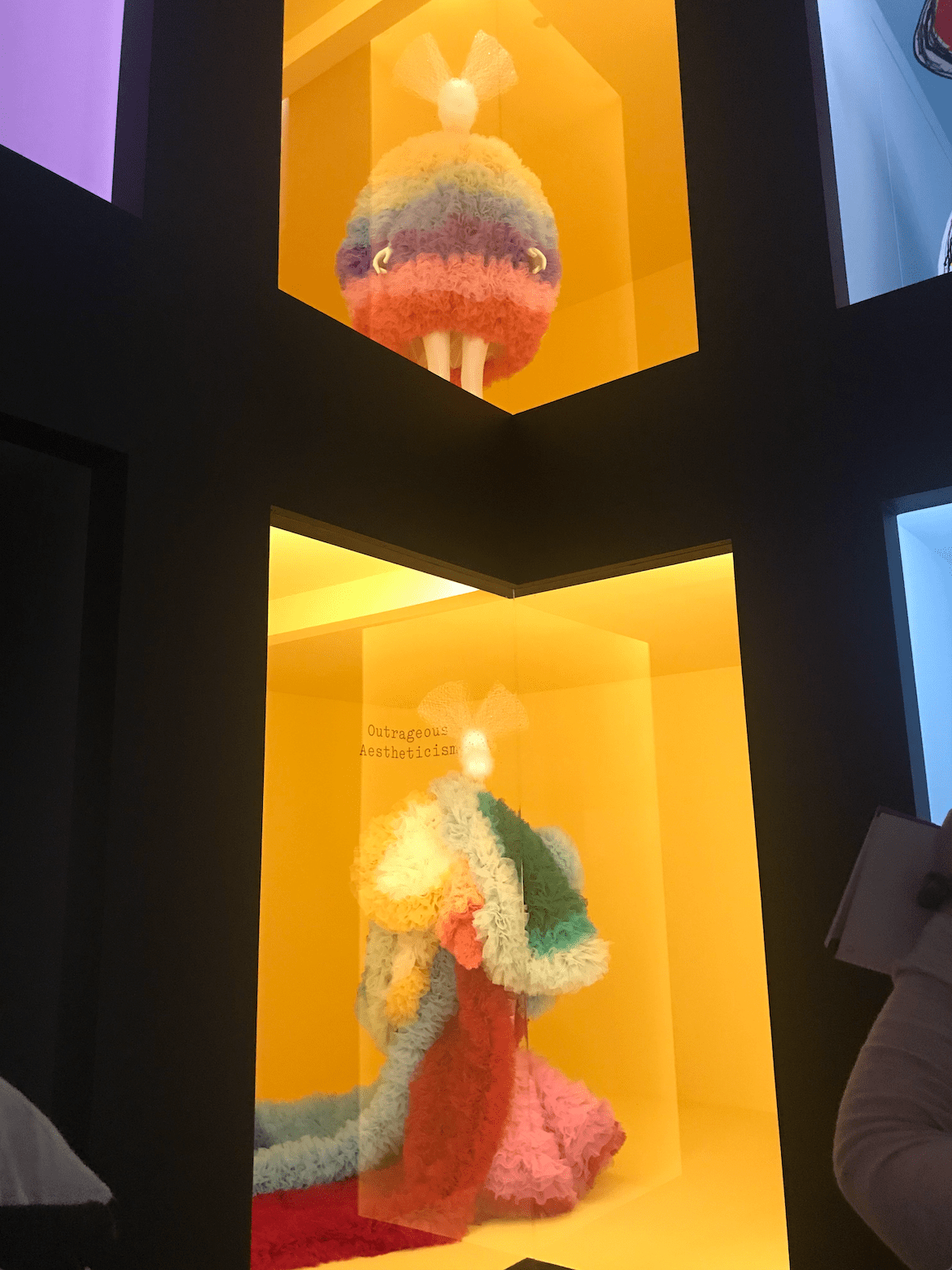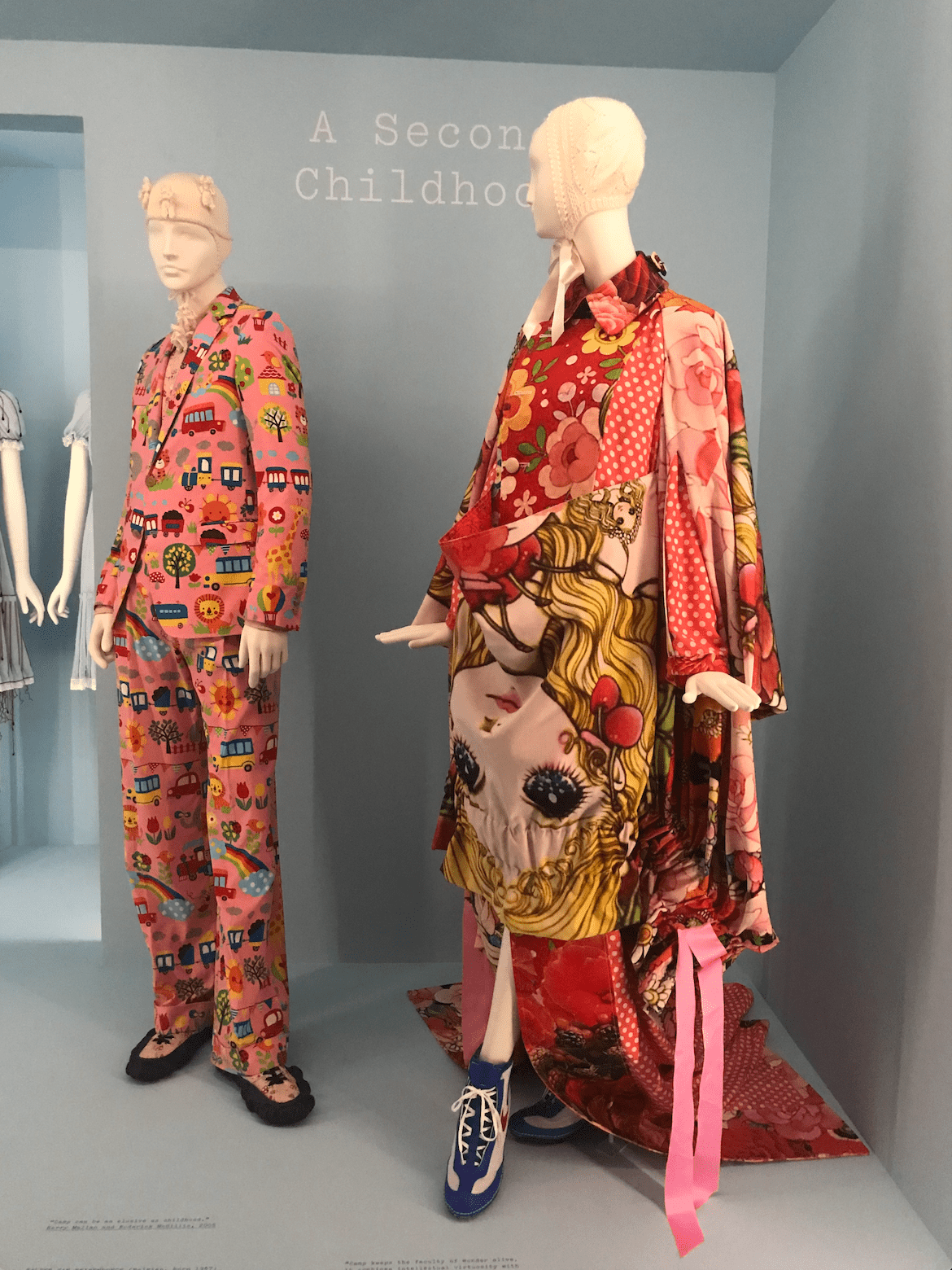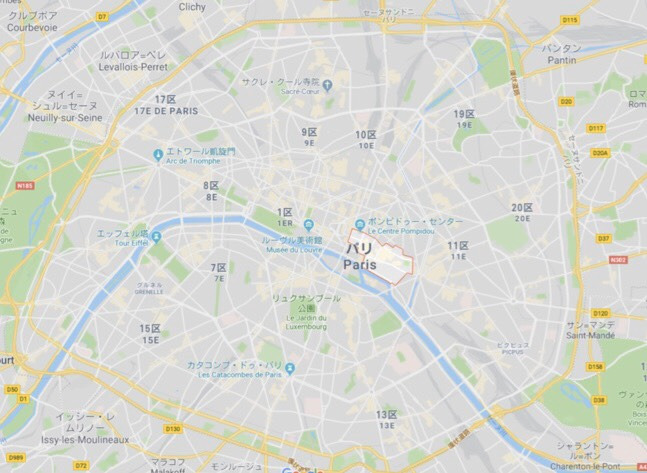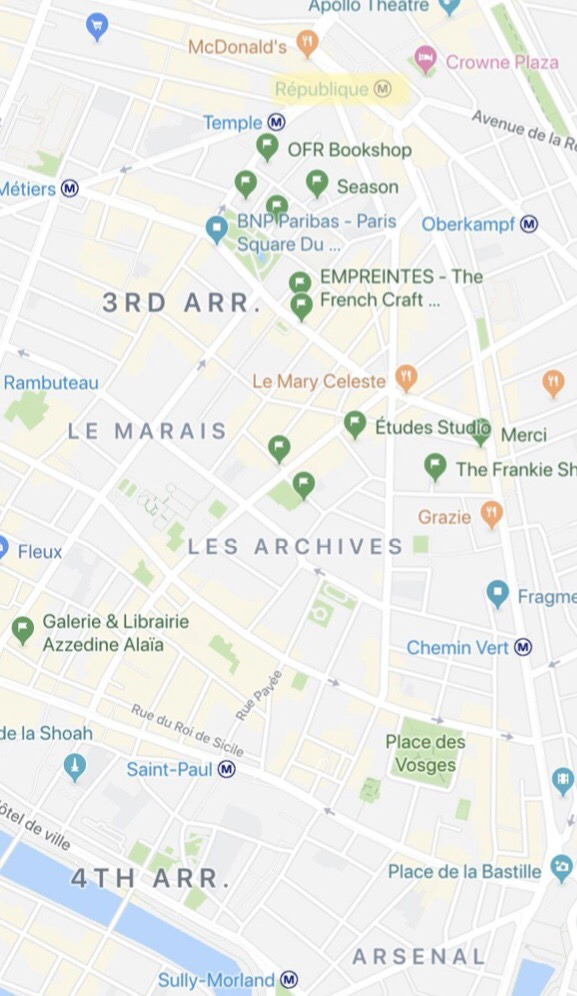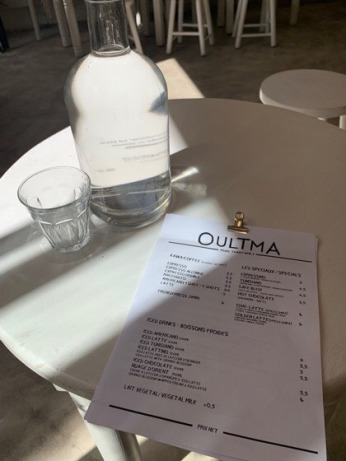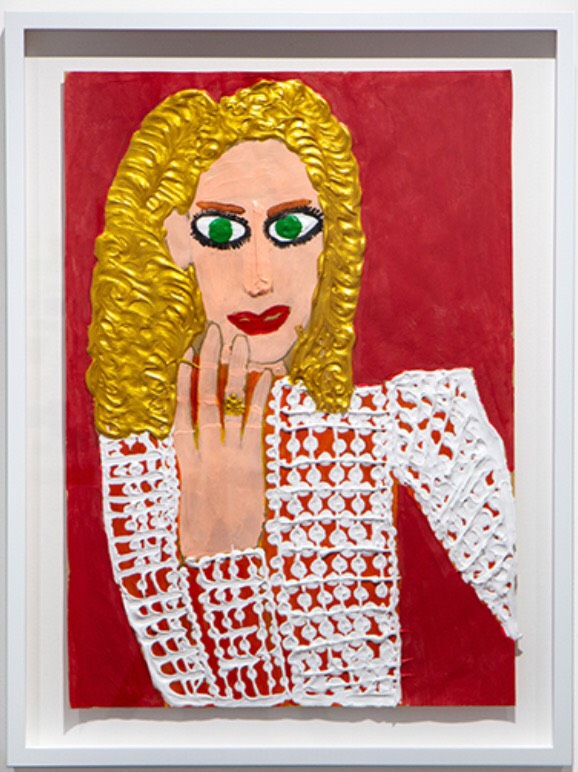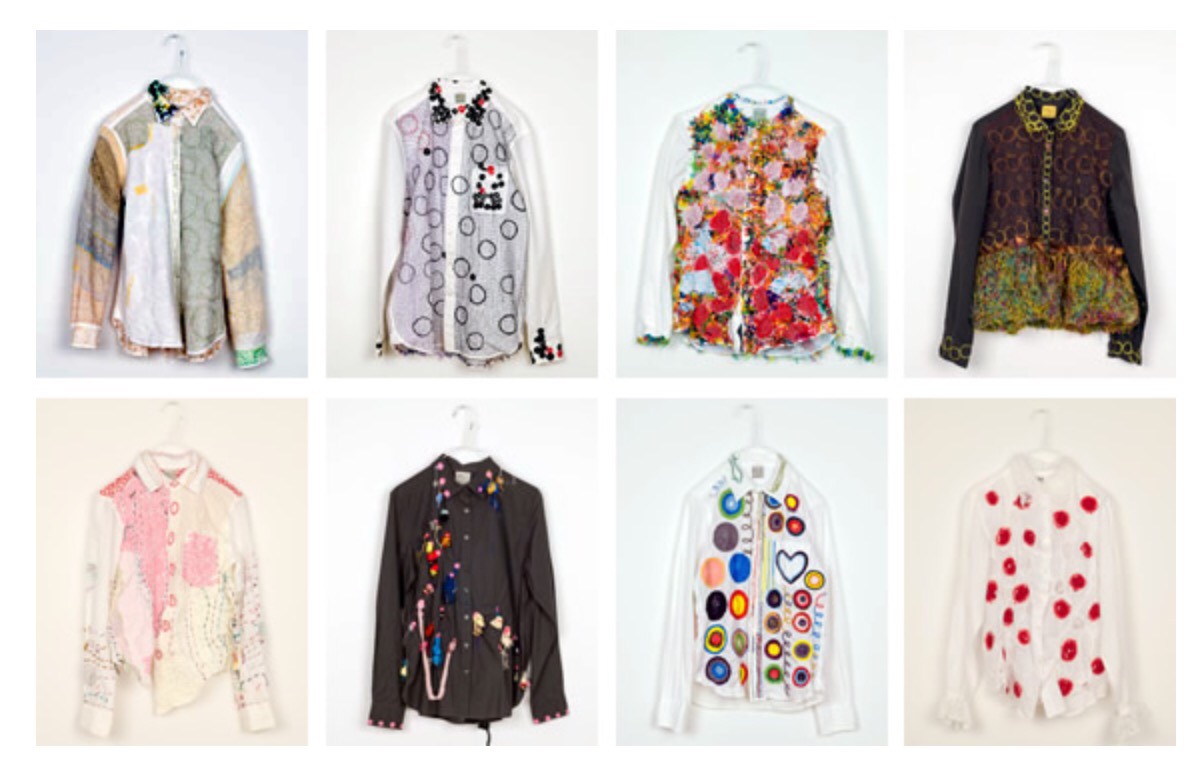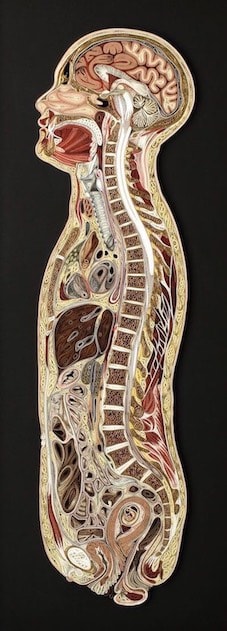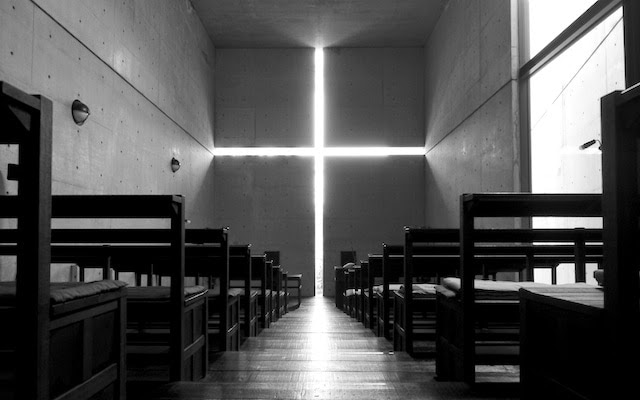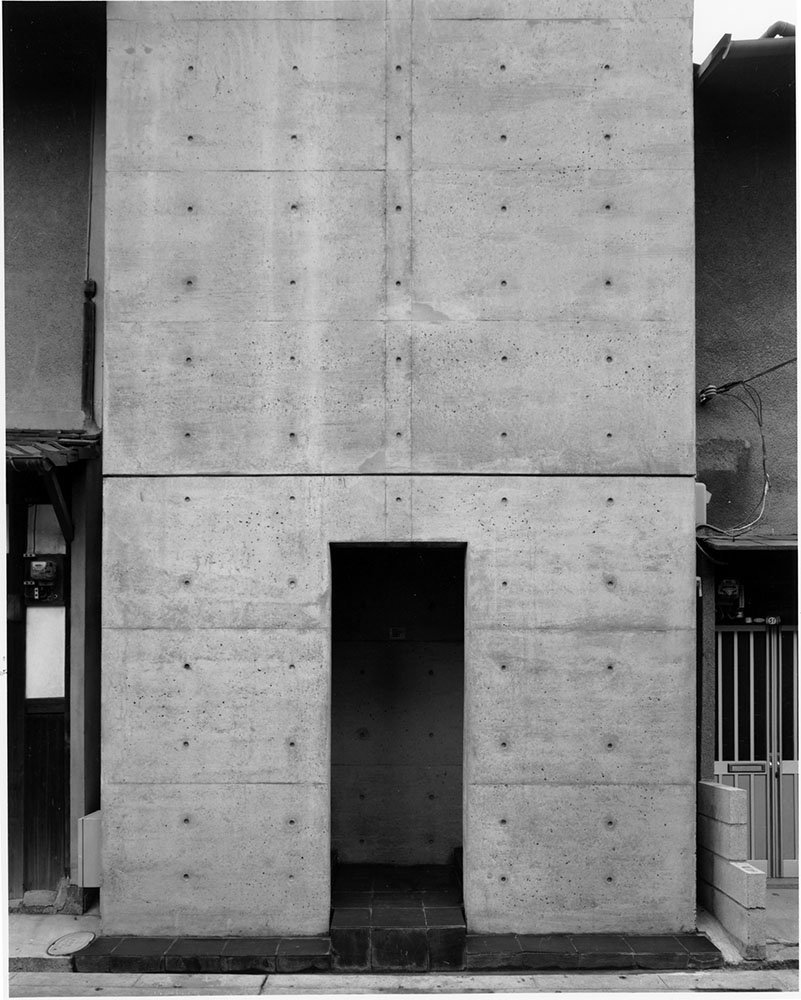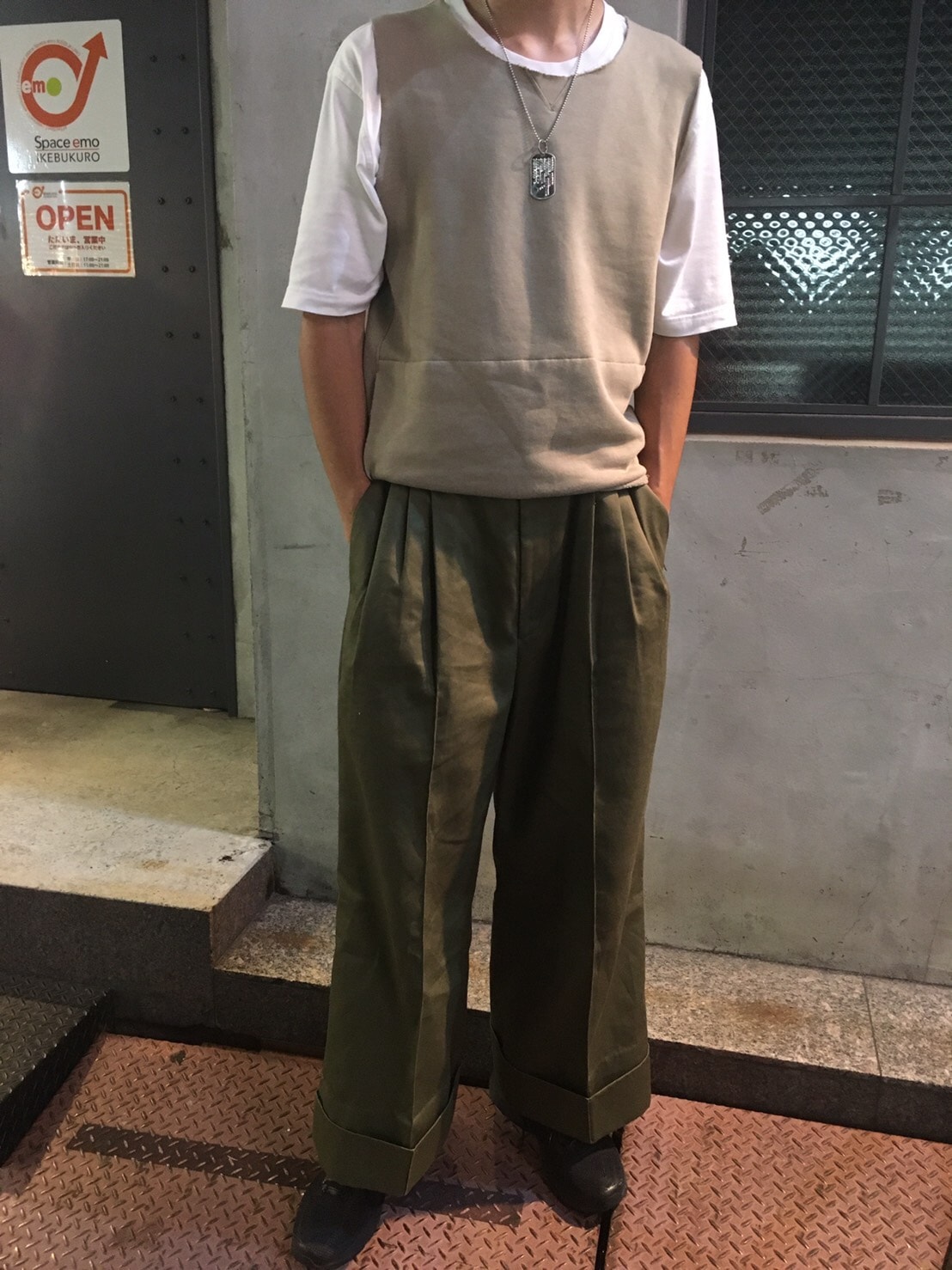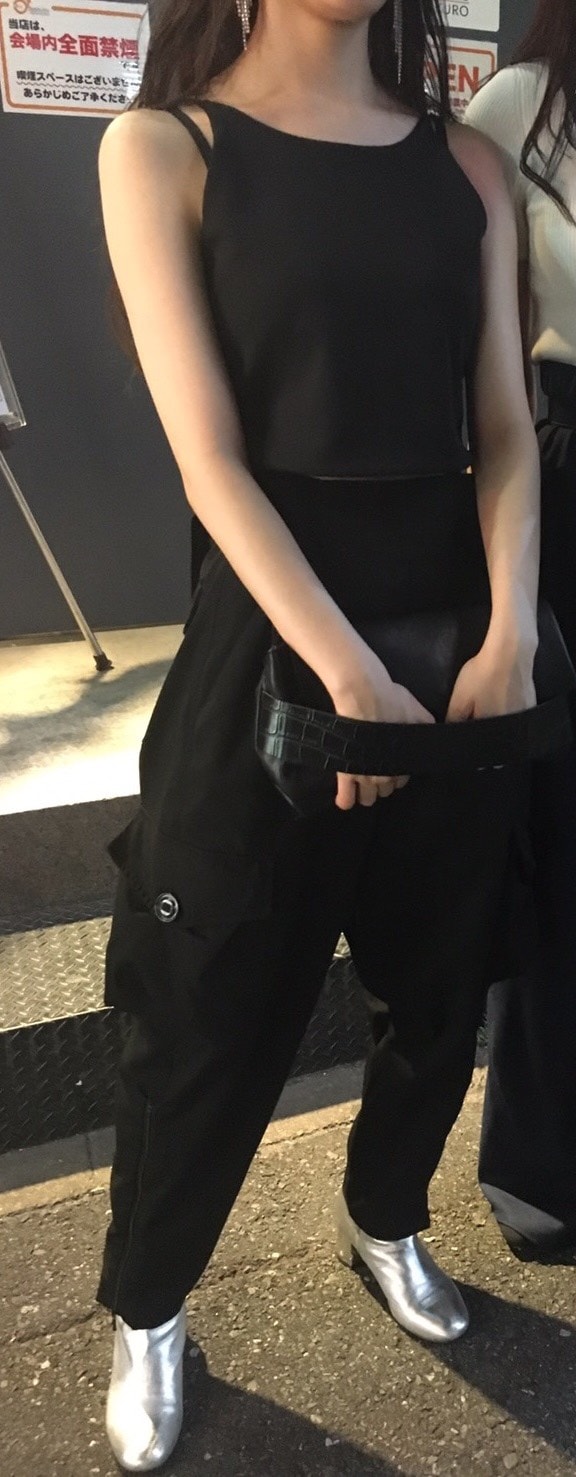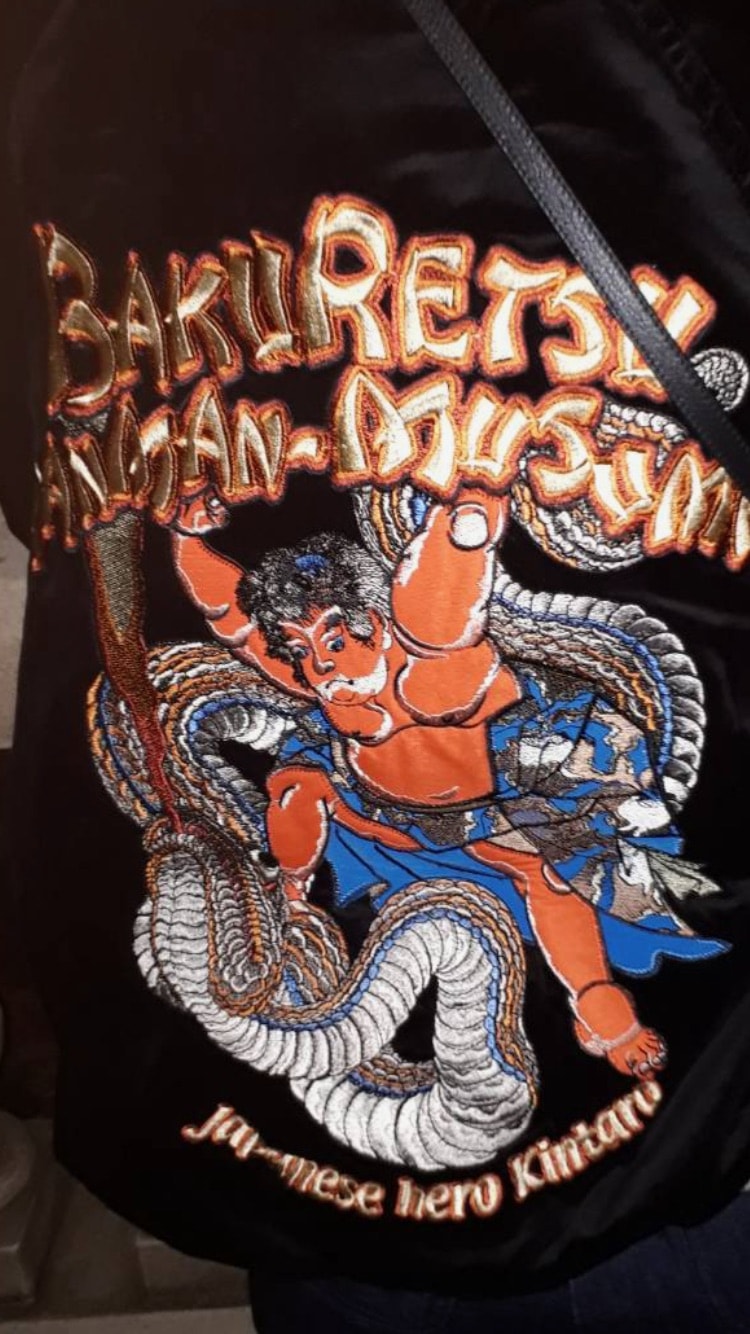2021
-
人と違うということ
Minagi Shinohara 2021. 9.28 by Keio Fashion Creator
-
見えないファッション
yuma kumatoriya 2021. 9.21 by Keio Fashion Creator
-
みんなに持って欲しいマインド
Koki Kanamori 2021. 9.21 by Keio Fashion Creator
-
流行のサイクル
nao matsushita 2021. 9.21 by Keio Fashion Creator
-
Met Galaの野次馬をした話
Momoko Sugita 2021. 9.21 by Keio Fashion Creator
-
魅惑のグルメエッセイ
Hiyori Iwase 2021. 9.14 by Keio Fashion Creator
-
ゴルチエのプレタポルテ復活とsacai×Jean Paul Gaultier のカプセルコレクションについて
ryotaro hayashi 2021. 9.14 by Keio Fashion Creator
-
それぞれ違う人間
kokona umebayashi 2021. 9.14 by Keio Fashion Creator
-
one of the top
akari ono 2021. 9.14 by Keio Fashion Creator
-
私の特技
konoko 2021. 9.07 by Keio Fashion Creator
-
かつての服たちへ
Kyoka Hashimoto 2021. 9.07 by Keio Fashion Creator
-
僕の好きなマガジン
daiki adachi 2021. 9.07 by Keio Fashion Creator
-
自意識の話
akari ono 2021. 9.07 by Keio Fashion Creator
-
街の風景
Kyo Ishibashi 2021. 8.31 by Keio Fashion Creator
-
ルッキズムについて
sara takeuchi 2021. 8.31 by Keio Fashion Creator
-
映画とファッション
YU MURAI 2021. 8.31 by Keio Fashion Creator
-
歳を取ること、スタイルの変容、そしてダンディズムについて
haruki sugiyama 2021. 8.31 by Keio Fashion Creator
-
服を介して
SHIORI NAKAMURA 2021. 8.24 by Keio Fashion Creator
-
服と私の関係性
Marina Miyake 2021. 8.24 by Keio Fashion Creator
-
服を通じて日常から私が感じること
meguri takano 2021. 8.24 by Keio Fashion Creator
-
きたい
Hinako Kutara 2021 8.24 by Keio Fashion Creator
-
アンドレイ・タルコフスキー『ノスタルジア』を読む
Yuto Tanishiki by Keio Fashion Creator